新興国ってどうなの?という疑問を持っている方へ記事を書きました。

皆さんはジェレミー・シーゲル教授をご存じでしょうか?ジェレミー・シーゲル教授の書籍について書きました。
75歳の高齢となりますが、米国のCNBCなどで定期的に出演している、ジェレミー・ジェームズ・シーゲル教授をご存じでしょうか?
2020年のコロナショックで株価が下落するさなかにも「米国株を買い続づけなさい」と言っていた方です。
今回はジェレミー・シーゲル教授の書籍を紹介します。
新興国投資を始める前や、加熱する市場に挑む前に
ぜひ読んで欲しい良本となっております。
人物紹介
氏名:ジェレミー・ジェームズ・シーゲル
生年月日:1945年11月14日
ペンシルバニア大学ウォートンのファイナンスの教授。
CNN、CNBC、NPRなどに定期的に出演し、Kiplinger’s PersonalFinanceとYahoo!へコラムを執筆。
過去200年という長期の過去データを分析しており、TVでシラー氏と、市場とリターンについてテレビで頻繁に議論し、金融メディアの有名人となった。
書籍の紹介
こちらの書籍は、投資関連の本を初めて読む方でも難なく読めると思います。
書籍の主たる内容
私が研究したところでは、PERはGDP成長率より将来リターンを占う上でより有効である。
ウィズダムツリーのウェブキャスト ‐ シーゲル教授の言葉
シーゲル氏はこれまでに、新興国やバリュー株を推奨していましたが、背景には研究があるそうです。
著書にかかれている内容がこの研究の一部となっております。
シーゲル氏の『株式投資の未来』書き出しで、1955年にスタンダード・オイルとIBMに投資した場合のトータルリターンの比較が書かれています。
| 1955年の指標 | IBM | スタンダード・オイル |
| 売上高(一株あたり) | 12.2% | 8.0% |
| 配当(一株あたり) | 9.2% | 7.1% |
| 利益(一株あたり) | 10.9% | 7.5% |
| セクター成長率 | 14.7% | ▲14.2% |
当時の”IBM”と”スタンダード・オイル”を比較すると、全ての指標において、IBMの方が優れていました。
そして分析対象の約50年後には、IBMは当時に比べ随分成長しました。
しかし、長期保有の場合において、配当と株価上昇を足し合わせたトータルリターンはスタンダード・オイルの方が良かった結果になっています。
これはPERは高くなっていたためでした。
- 長期投資の場合、配当の再投資によって株式上昇率より上回る時がある
- バリューはPERが一つの指標になる
- 国別でもバリューの考え方が当てはまる
トータルリターンの計算式
トータルリターン = 株価※1 ✖ 株式数※2 - 取得単価
※1:株価上昇率
※2:配当を再投資して増やす
この書籍では“株価”を上げるための株価上昇率よりも
“株式数”を増やす配当再投資の方が勝る
という結論にいたっております。
なぜ?こうなる
『PERが高い』ということが株価上昇率を押し下げている要因となっています。
長期投資の期間
約50年での結果から解説されていますが、何年間必要か分析しました。
対象はIBMとスタンダード・オイルとすしました。
その結果、最低15年以上の保有が必要となりました。
15年が”グロース株”と”バリュー株”の分岐点となりそうです。
他の銘柄での検証結果
投資家のリターンは“実際の増益率”と“投資家の期待”の差で決まる。
株式投資の未来 ‐ シーゲル教授の言葉
実際の増益率:前期と当期のEPS上昇率
投資家の期待:PER=株価 ÷ 予想EPS
この二つのデータと配当利回りから、S&P500の銘柄についても検証を行っております。
書籍の中では、銘柄の選定方法として
具体的にPER、EPS上昇率、配当利回り
以上の3点での参考数値を書いています。
今後の長期投資で実際に参考になる良本となります。
グローバルな視点で考えると
シーゲル教授は国別にも、この考え方が当てはまるといっております。
そのため、現在の米国株は最も割高であり、中国市場は今だPERが低値で放置されています。
先進国のPERも米国ほどではないにしても高PERです。
他の記事に新興国株について記載しました。
新興国へ投資する際に注目すべきポイントについて。
新興国株は成長率に相関していないことについて。
私見となりますが、将来有望な新興国をピックアップしました。

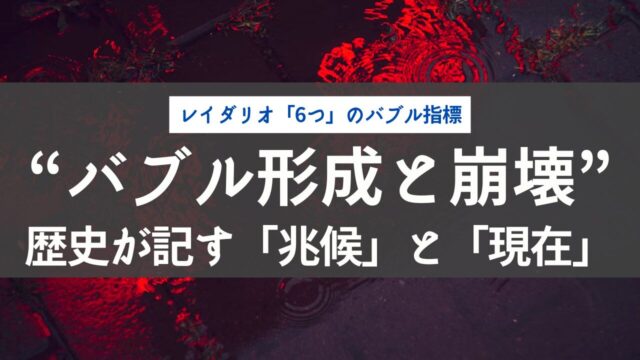
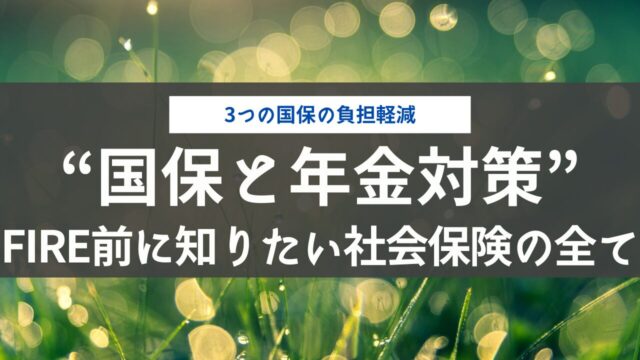
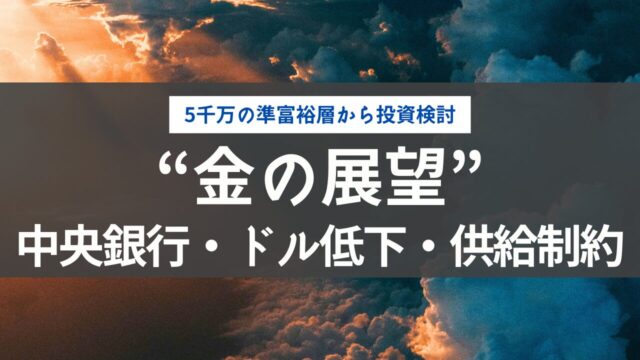
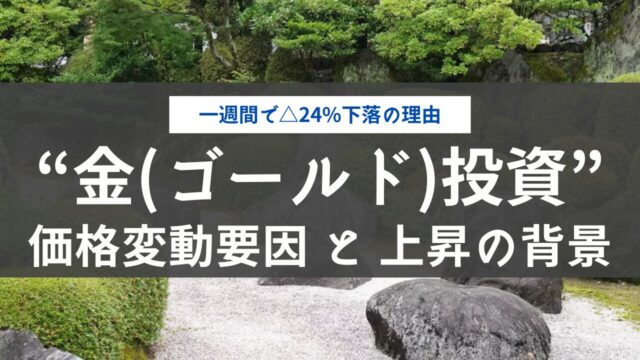
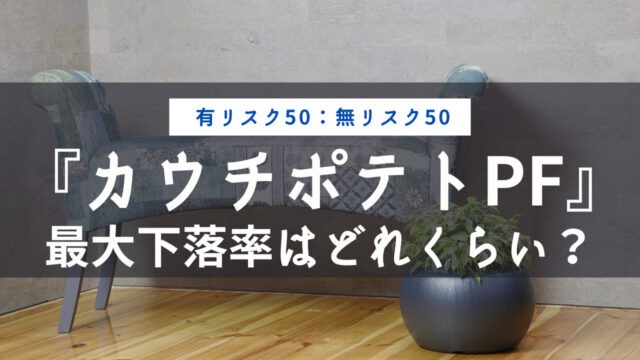
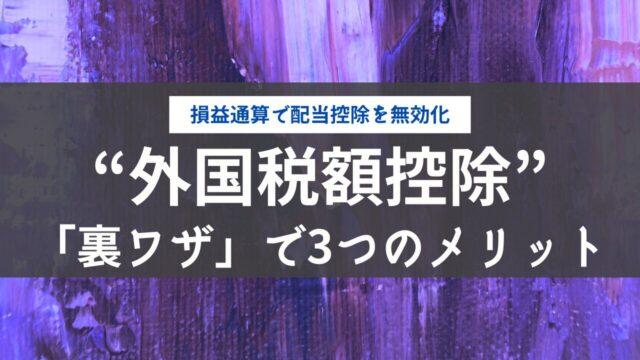
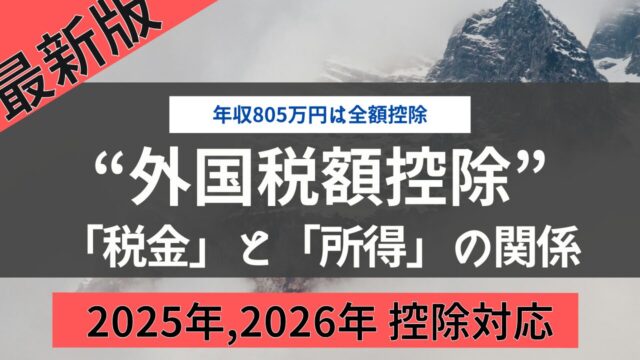
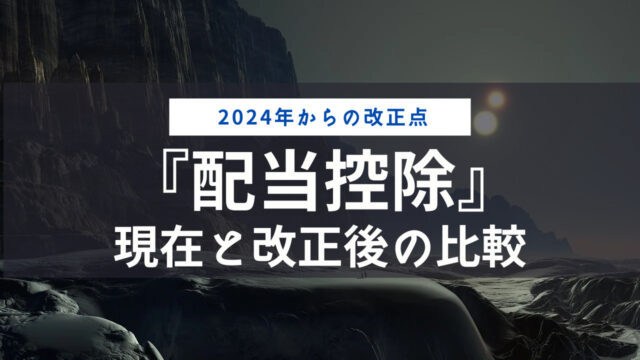
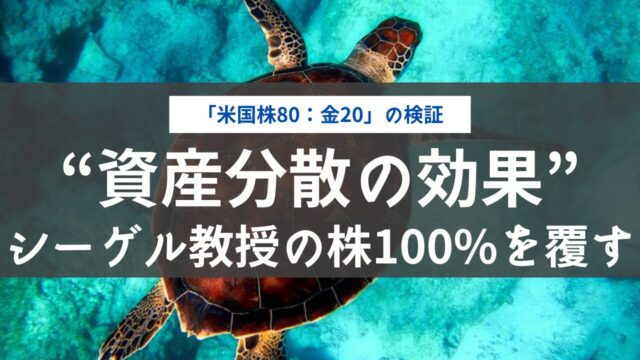


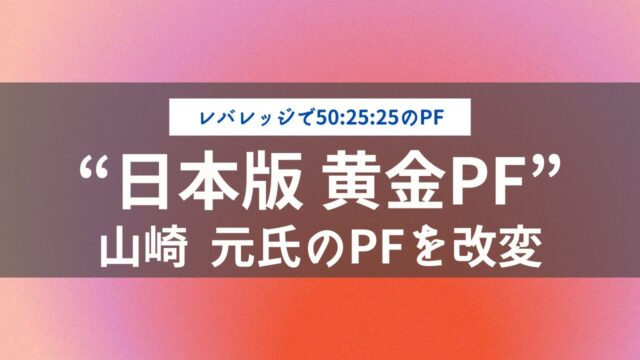
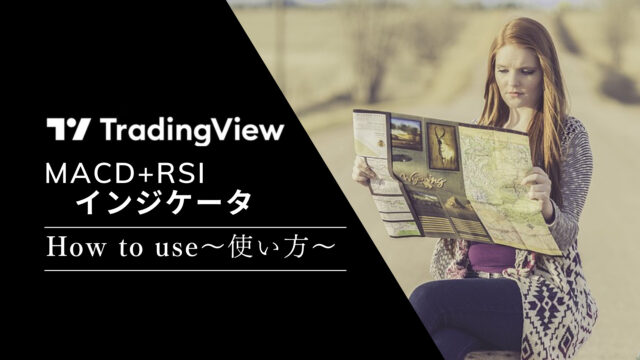


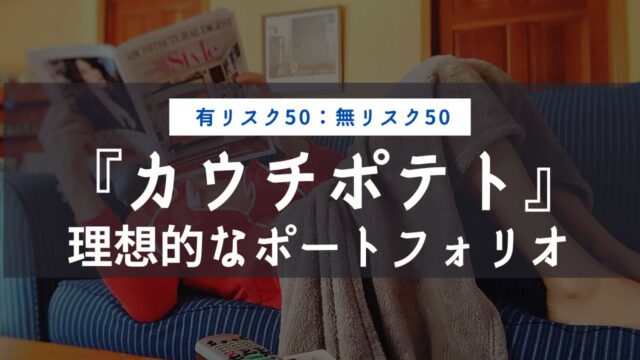

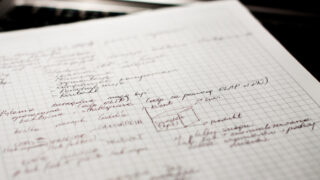




コメント