両親を「社会保険の扶養」に入れるデメリットはなに?
デメリットを軽減する方法はないの?
扶養には「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。
この2つの扶養は、各々に「扶養」を選択することが可能です。
「こんなはずではなかった」
となる前に、扶養に入れた時のデメリットを確認して、扶養にするかを検討してください。
この記事は、対象者を“公務員”や“サラリーマン”などの労働者に限り可能な、社会保険の扶養について解説します。
記事を読むことで、ご両親や奥様を扶養としたら良いのかを、経済的な視点で正しく選択できるようになりますので、最後までご覧ください。
記事が、タメになったと思われたら、“SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
健康保険扶養のメリット・デメリットまとめ
| 住居 | 世帯 | 条件 | 介護 | 医療 |
|---|---|---|---|---|
| 同居 | 同一世帯 | 簡単 | 負担増 | 変化あり |
| 同居 | 別世帯 | 簡単 | 変化なし | 変化あり |
| 別居 | 別世帯 | 厳しい | 変化なし | 変化あり |
表を見ると、扶養に入れる時には事前に別世帯とした後に、扶養とする方がデメリットを抑えることができることがわかります。
高額療養費制度については扶養に入れた時点で、扶養者の条件に変化します。
これについてはデメリットで詳しく後述します。
「社会保険の扶養」のメリットについて

扶養に入れるメリットは、扶養者の負担が増えることなく、被扶養者の保険支払いが無くなることがメリットです。

そんなに良いことなの?

年間で数十万の負担が減ります
| 前年(1月~12月)年収 | 年間国保料(目安) |
|---|---|
| 300万円 | 約24.8万円 |
| 400万円 | 約33.3万円 |
| 500万円 | 約42.5万円 |
・退職翌年の国保は前年1月から12月の所得で計算されます。
・保険料は4月から3月となり、退職した年の所得が反映されるので高額となります。

働いていないのに何で金額が大きいの?
国民健康保険料は昨年働いた年収を基に計算されます。
そのため、現役で働いていた保険料の負担となるため、退職してから翌年まで負担が大きいです。

100万円から1,000万円までの詳細は下のボタンから確認できます
・下の表は東京都新宿区の2023年度の目安表です。
| 総所得金額等 | 年間保険料 (40歳未満) |
1カ月あたり (40歳未満) |
年間保険料 (40~64歳) |
1カ月あたり (40~64歳) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 114,763円 | 9,564円 | 140,938円 | 11,745円 |
| 150万円 | 162,713円 | 13,559円 | 197,638円 | 16,470円 |
| 200万円 | 210,663円 | 17,555円 | 254,338円 | 21,195円 |
| 250万円 | 258,613円 | 21,551円 | 311,038円 | 25,920円 |
| 300万円 | 306,563円 | 25,547円 | 367,738円 | 30,645円 |
| 350万円 | 354,513円 | 29,543円 | 424,438円 | 35,370円 |
| 400万円 | 402,463円 | 33,539円 | 481,138円 | 40,095円 |
| 450万円 | 450,413円 | 37,534円 | 537,838円 | 44,820円 |
| 500万円 | 498,363円 | 41,530円 | 594,538円 | 49,545円 |
| 550万円 | 546,313円 | 45,526円 | 651,238円 | 54,270円 |
| 600万円 | 594,263円 | 49,522円 | 707,938円 | 58,995円 |
| 650万円 | 642,213円 | 53,518円 | 764,638円 | 63,720円 |
| 700万円 | 690,163円 | 57,514円 | 821,338円 | 68,445円 |
| 750万円 | 738,113円 | 61,509円 | 878,038円 | 73,170円 |
| 800万円 | 786,063円 | 65,505円 | 934,738円 | 77,895円 |
| 850万円 | 834,013円 | 69,501円 | 991,438円 | 82,620円 |
| 900万円 | 870,000円 | 72,500円 | 1,036,175円 | 86,348円 |
| 950万円 | 870,000円 | 72,500円 | 1,040,000円 | 86,667円 |
| 1,000万円 | 870,000円 | 72,500円 | 1,040,000円 | 86,667円 |
ちなみに、75歳以上となると、国民全員が「後期高齢者医療制度」へ変わるため、扶養に入れて支払い免除とできるのは、74歳までです。
話を戻しますと、社会保険に加入するサラリーマンであれば、扶養の概念がありますので、国民保険料が上がったとしても社会保険の負担は増えません。

サラリーマンの特権だね
社会保険料が増えない理由

国民健康保険は社会保険に加入できない幅広い人を対象にしています。
そのため、加入者一人一人が独立した被保険者とみなされるため、扶養の概念がありません。
その一方、社会保険は会社員や公務員など労働者を対象とした制度です。
労働者の経済的負担を軽減し、安定した生活を支援するために扶養の概念があります。
ちなみに、労働者の社会保険料は年度初頭の3ヶ月の総支給額を基に決定されています。

具体的にどの3ヶ月ですか?

4.5.6月の給与です
4月の給与が、その前月働いた労働時間に対して決定する場合には、3月から5月の労働に対して決定されます。
「社会保険の扶養」のデメリットについて

繰り返しになりますが、同一世帯とするとデメリットが2つあります。
別世帯にしたとしても、高額療養費制度の改悪は避けることができません。
ではまず、高額療養費制度について解説します。
高額療養費制度の変化
高額療養費制度とは、被扶養者が「交通事故」や「病気」を患って手術などの高額な医療費の負担が発生した時に、負担を和らげてくれる制度のことです。

どうすれば負担が減るの?

月に支払う限度を超えた額が免除になります
高額療養費制度の限度額は、被保険者の「標準報酬月額」によって決定します。
つまり、被扶養予定の親の収入が小さくて、扶養でないときの限度額35,400円(非課税世帯)が、扶養となると約8万円へと2倍以上に負担が増加します。
| 所得区分 | 自己負担限度額 (月額) |
多数回該当 (4回目以降) |
|---|---|---|
| 課税世帯 (所得901万円超) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 課税世帯 (所得600万超~901万円) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 課税世帯 (所得210万超~600万円) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 課税世帯 (所得210万円以下) |
57,600円 | 44,400円 |
| 非課税世帯 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |

多数回該当ってなに?

過去1年に4回以上で上限がさらに下がる制度です
高額療養費制度で考えたいのが、単発での医療費なのか?
それとも、何か月も続く医療費なのか?
この違いです。
例えば、高齢化による再手術等で数か月にわたって療養費の出費が出るときは痛手となりますので、慎重な判断が求められます。
・高齢や持病持ちで傷病が出やすい→扶養としない
余談となりますが、75歳以上の高額療養費制度は下のボタンをタップで表示されます。
| 所得区分 | 自己負担限度額 (月額) |
多数回該当 (4回目以降) |
|---|---|---|
| 課税世帯 (所得690万円以上) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
| 課税世帯 (所得380~690万円未満) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
| 課税世帯 (所得145~380万円未満) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
| 一般 (所得145万円未満) |
57,600円 | 44,400円 |
| 非課税世帯 (住民税非課税 世帯) |
24,600円 | 15,000円 |
| 非課税世帯 (全員の所得が0円) |
15,000円 | 15,000円 |
介護関連費用の増加

介護関連費用は、「同一世帯」となっている場合に負担額が大きくなるものです。

負担が増える介護関連費用はこちらの3つです
一般的な年金収入の非課税世帯と一般的な課税世帯を比べてみると、1年あたり約130万円の差が生じます。
介護期間は平均で4年から4年7か月となりますから、通算して約520万円~約610万円の出費の差が生まれます。

負担ハンパねぇ
介護保険料の増加
| 年金収入額の目安 | 非課税世帯 (月額/年額) |
課税世帯 (月額/年額) |
|---|---|---|
| 80万円以下 | 約1,800円/約22,000円 | 約5,400円/約65,000円 |
| 80万円超〜120万円以下 | 約2,600円/約31,000円 | 約6,400円/約77,000円 |
| 120万円超 | 約4,400円/約53,000円 | 約9,000円/約108,000円 |
※区によって若干差が生じます。
非課税世帯は同じ年金収入でも、課税世帯に比べ介護保険料が3倍ほど大きくなります。
介護保険料の詳細は下のボタンをタップしてください。
| 年金収入額の目安 | 年額(円) | 月額(円) |
|---|---|---|
| 80万円以下 | 約22,000 | 約1,800 |
| 80万円超〜120万円以下 | 約31,000 | 約2,600 |
| 120万円超 | 約53,000 | 約4,400 |
| 年金収入額の目安 | 年額(円) | 月額(円) |
|---|---|---|
| 80万円以下 | 約65,000 | 約5,400 |
| 80万円超 | 約77,000 | 約6,400 |
| 125万円未満 | 約81,000 | 約6,800 |
| 125〜210万円未満 | 約91,000 | 約7,600 |
| 210〜320万円未満 | 約108,000 | 約9,000 |
| 320〜500万円未満 | 約124,000 | 約10,300 |
| 500〜700万円未満 | 約145,000 | 約12,100 |
| 700〜1,000万円未満 | 約169,000 | 約14,100 |
| 1,000万円以上 | 約192,000〜230,000 | 約16,000〜19,200 |
高額介護サービス費用の増加

高額介護サービスってなに?

介護サービスの自己負担上限です
介護サービスは増加する費用の中で、一番負担が大きくなります。
・5つの段階で区分されており、上限がことなる。
つまり、医療費の「高額療養費」の介護版のことです。
高額療養費制度と異なるのは、多数回該当という制度がありません。
そのため、高額介護サービス費が毎月かかってくるため、負担は相当大きくなります。
| 区分 | 該当条件 | 月額上限 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者 | 15,000円 |
| 第2段階 (個人) |
住民税非課税世帯で公的年金等収入 +その他所得が80万円以下 |
15,000円 |
| 第2段階 (世帯) |
上記世帯で複数人が介護サービスを 利用した場合の世帯合算上限 |
24,600円 |
| 第3段階 | 住民税非課税世帯で 第1・第2段階以外の方 |
24,600円 |
| 第4段階 | 課税世帯 (所得:380万円未満) |
44,400円 |
| 第5段階 (前半) |
課税世帯 (所得:380万円~690万円未満) |
93,000円 |
| 第5段階 (後半) |
課税世帯 (所得:690万円以上) |
140,100円 |
・世帯:同一世帯で介護を受けた方が複数いる場合
介護サービスの負担の上限は、『世帯全員が住民税非課税』が必須条件となります。
そのため、親が年金暮らしで、非課税世帯だったとしても、同一世帯となるので、あなたの所得が380万円以上であると上限が93,000円となります。
平均介護期間は4年なので、約380万円の費用増加が推測できます。
介護施設の費用(老人ホーム)の増加

更に、介護施設の費用も増加します

高額介護サービスで抑えられないの?
高額介護サービスで抑えられるものは、介護保険が適用されるサービスのみとなります。
・訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護(デイサービス)
・短期入所(ショートステイ)
・福祉用具貸与 など
介護施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
地域密着型サービス
・グループホーム
・小規模多機能型居宅介護
対象外となるものの一例に、施設での食費や居住費については高額介護サービスの限度額に含まれておりません。
また、福祉のために住宅改修をした費用や特定福祉用具購入した時の費用も含まれていません。

下の表は全て自己負担となります
| 区分 | 年金収入等の目安 (世帯主) |
月額費用目安 (多床室) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 年金生活 非課税世帯 |
211万円以下(配偶者155万円以下) | 約7.5~8万円 | 居住費・食費の軽減措置適用、要介護3~5の場合 |
| 課税世帯 | 211万円超 | 約10~10.5万円 | 居住費・食費の軽減なし、要介護3~5の場合 |
| 段階 | 年金収入などの目安 | 預貯金など | 食費(月額) | 住居費(月額) |
| 第1段階 (非課税) |
生活保護・ 老齢福祉年金等 |
単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
約9,000円 (300円/日) |
ユニット型個室: 約26,400円(880円/日) ユニット型個室的多床室: 約16,500円(550円/日) 従来型個室: 約11,400円(380円/日) 多床室:0円 |
| 第2段階 (非課税) |
年金収入80万円以下 | 単身650万円以下 夫婦1650万円以下 |
約11,700円 (390円/日) |
ユニット型個室: 約26,400円(880円/日) ユニット型個室的多床室: 約16,500円(550円/日) 従来型個室: 約14,400円(480円/日) 多床室: 約12,900円(430円/日) |
| 第3段階① (非課税) |
年金収入80万円超120万円以下 | 単身550万円以下 夫婦1,550万円以下 |
約19,500円 (650円/日) |
ユニット型個室: 約41,100円(1,370円/日) ユニット型個室的多床室: 約41,100円(1,370円/日) 従来型個室: 約26,400円(880円/日) 多床室: 約12,900円(430円/日) |
| 第3段階② (非課税) |
年金収入120万円超 | 単身500万円以下 夫婦1,500万円以下 |
約40,800円 (1,360円/日) |
ユニット型個室: 約41,100円(1,370円/日) ユニット型個室的多床室: 約41,100円(1,370円/日) 従来型個室: 約26,400円(880円/日) 多床室: 約12,900円(430円/日) |
| 第4段階 (課税世帯) |
一般所得(最低値) | なし | 約43,350円 (1,445円/日) |
ユニット型個室: 約60,180円(2,006円/日) ユニット型個室的多床室: 約49,200円(1,640円/日) 従来型個室: 約35,130円(1,171円/日) 多床室: 約25,650円(855円/日 |
| 課税所得区分 | 自己負担割合 | 多床室 (月額) |
従来型個室 (月額) |
ユニット型個室的多床室 (月額) |
ユニット型個室 (月額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 380万円未満(年収約770万円未満) | 1割 | 約10万円 | 約11万円 | 約12.5万円 | 約13.5万円 |
| 380万~690万円未満(年収約770~1160万円) | 2割 | 約12~13万円 | 約13~14万円 | 約15万円 | 約16万円 |
| 690万円以上(年収約1160万円以上) | 3割 | 約14~15万円 | 約15~16万円 | 約17万円 | 約18万円 |

負担が大きすぎる…
こういった、介護関連の負担増加は、「同一世帯」ということがネックになっています。
負担を解消するには、「別世帯」とすることで解決することができます。
では次に、どうやって別世帯にするかを解説します。
世帯分離で別世帯へ

実は、親と同居していても「別世帯」とすることが可能です。
同居したまま別世帯とすることを、「世帯分離」と言い、別世帯とすることで、親を非課税世帯とすることも可能です。
・生計が別である証明を求められるケースもあります。
※介護費用や保険料削減を前面に出すと、不適切な理由で却下される可能性があります。

デメリットはないの?

親が高収入であれば負担が生じる場合もあります
・別世帯の被扶養要件から外れる可能性があります。
・親の収入に応じて国民健康保険が発生します。
勤務先の手当
・扶養手当などの対象外となるケースがあります。
親が別世帯で非課税世帯となる場合では、デメリットが小さくなります。
住民税の非課税世帯についての要件について別の記事で詳しく解説しています。>>住民税の非課税要件について
まとめ
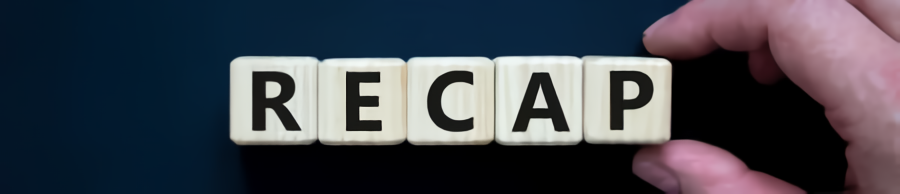
高額療養費制度は同一世帯や別世帯を関係なく、扶養者の収入に応じて変化してしまいます。
そのため、「社会保険の扶養」を考えるときに重要な事項は持病の有無となります。
被扶養者が若く、医療費が高額となるケースが万一であれば盲目的に社会保険の扶養に入れた方が良いでしょう。
一方、高齢となる両親を扶養にする場合は、万が一の介護負担を減らすために、同居であっても世帯分離で世帯を分けておくことが賢明でしょう。
記事が、タメになったと思われたら、“SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励みになります。
関連記事
社会保険の扶養へ入れる条件を含め、サラリーマン向けに「社会保険の扶養」について詳しく徹底的に解説しました。>>社会保険の扶養
2024年以降で確定申告を行うと、配当金への住民税の課税方法が強制的に改訂されることに変わりました。こちらの記事で、節税となる所得ラインについて記載しています。>>新制度の配当控除
手取りを大きくするためには「節税」が必要です。こちらの記事ではサラリーマンでもできる節税術について解説しています。>>サラリーマンの節税

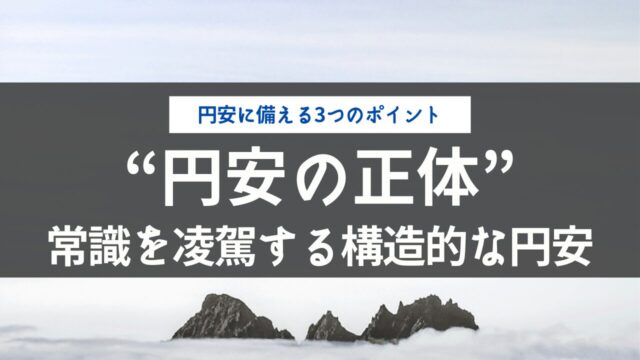
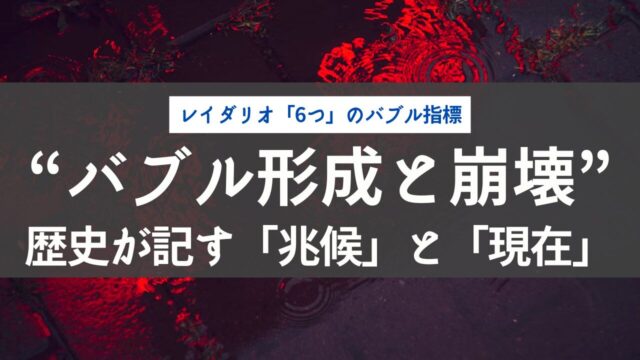
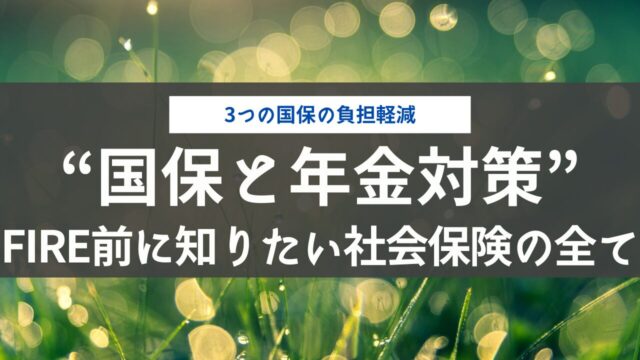
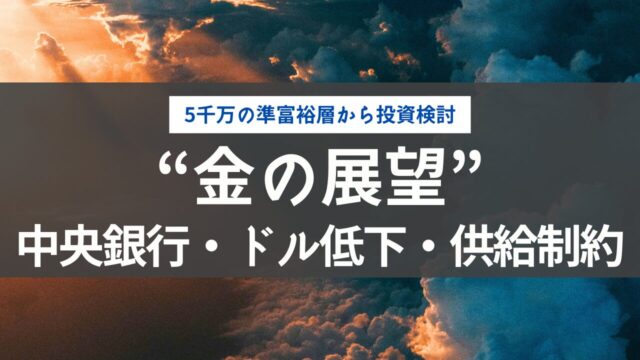
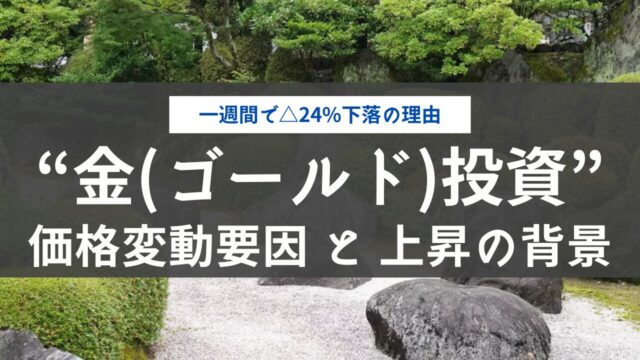
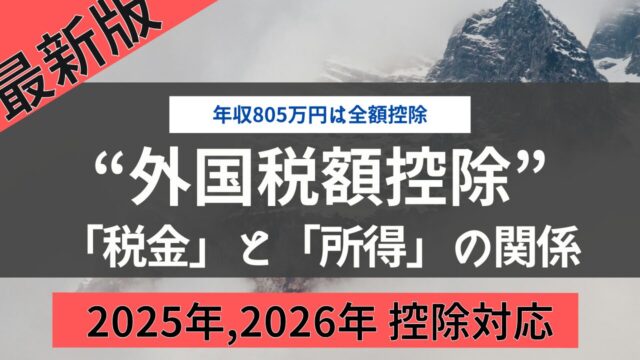
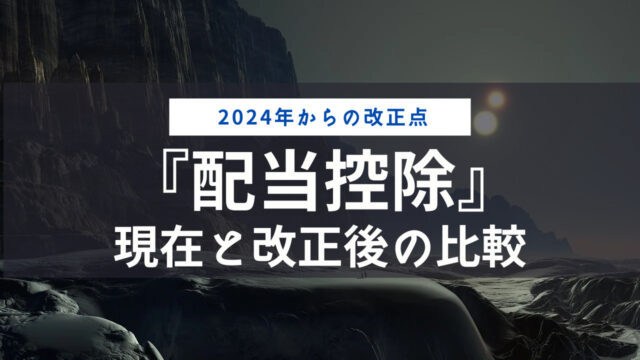
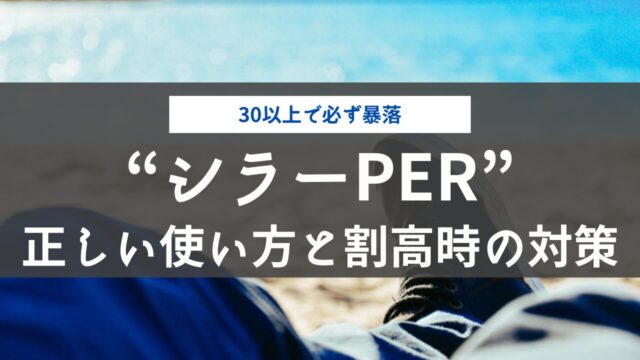


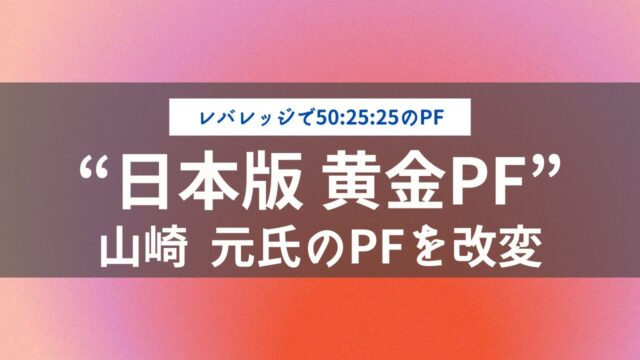
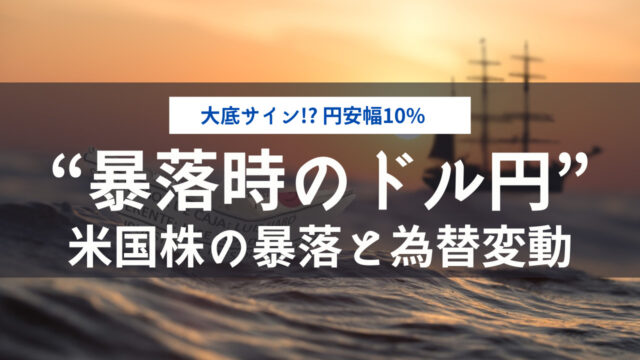

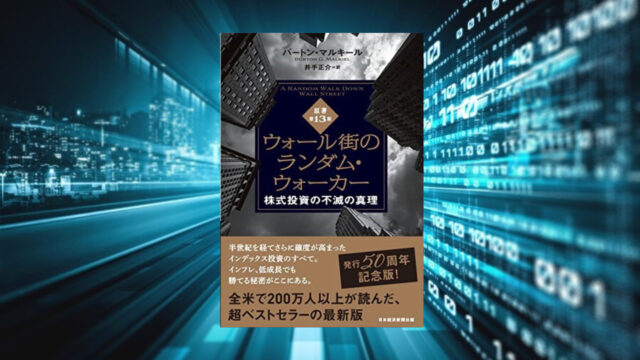



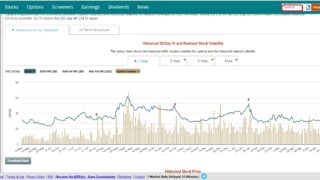
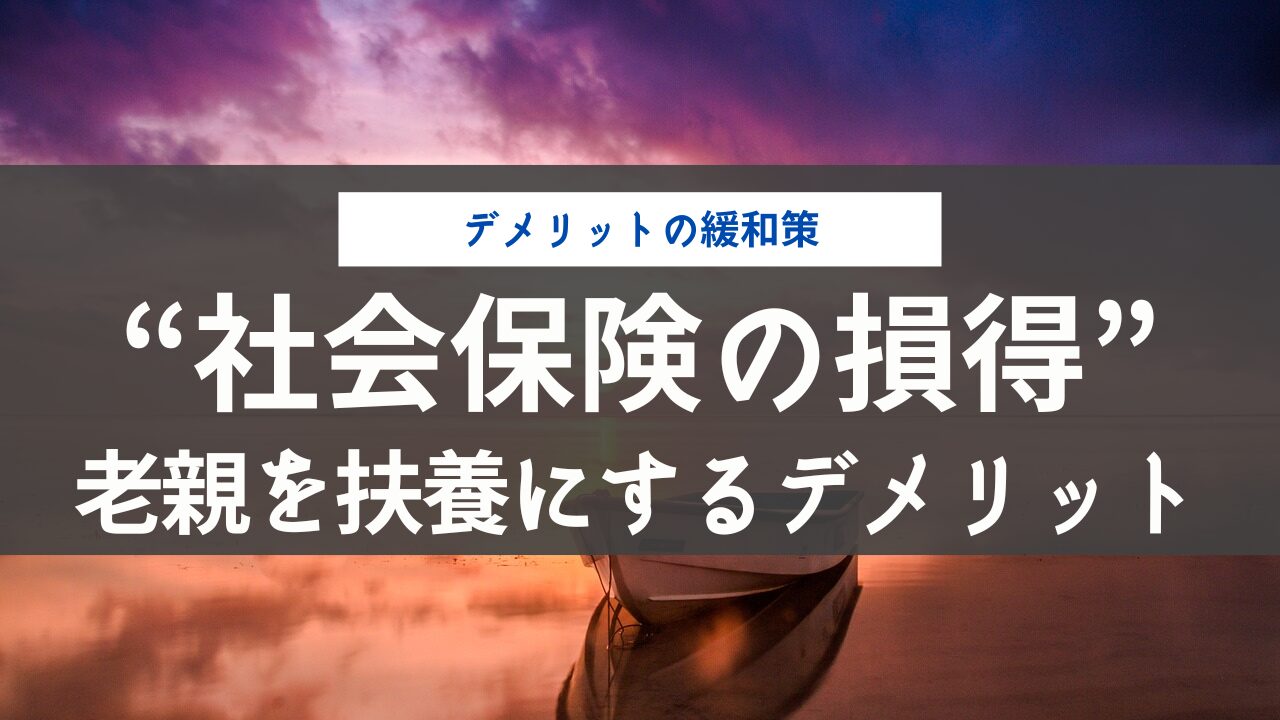
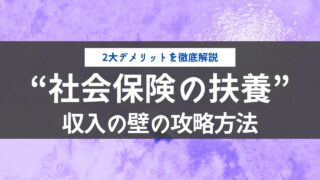
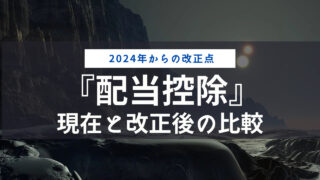
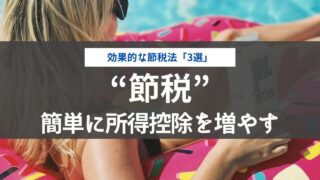

コメント